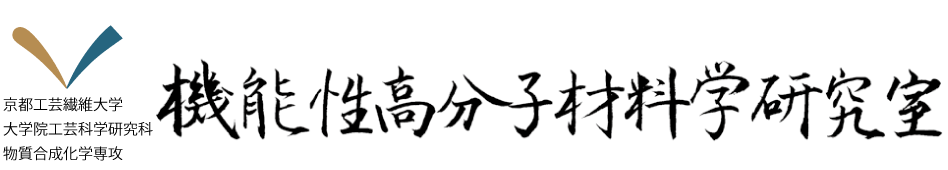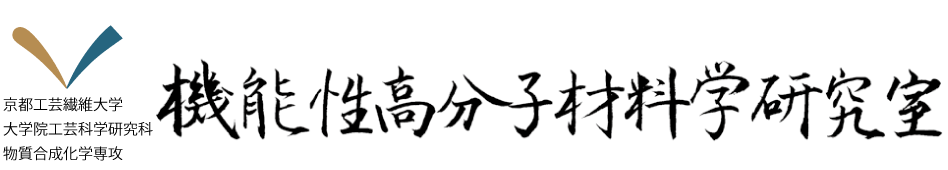分子量の小さいモノマーとポリマーの中間に位置するオリゴマーは、高分子にはない特徴ある性質を示し、反応中間体としても有用です。このオリゴマーに種々の反応性官能基を導入したものが、反応性オリゴマーです。導入する反応性官能基の種類により、オリゴマーの反応特性が異なり、多様な反応性を付与することができます。例えば、重合性官能基を導入すると、モノマーとして働くオリゴマー(マクロモノマー)になり、重合を開始するような官能基を導入すると、開始剤として働くオリゴマー(マクロイニシエーター)になります。これらの反応特性は、低分子のモノマーや開始剤とは大きく異なり、得られる高分子も特徴的であるため、非常に興味深い研究対象です。
オリゴマーに種々の官能基を導入し、官能基の反応性に及ぼすオリゴマー鎖の影響を調べると同時に、オリゴマー鎖によって反応系に形成される集合構造による反応制御について研究しています。また、反応性オリゴマーを反応中間体として用いると、より多彩な機能を有する高分子の合成が可能となります。そこで、反応性オリゴマーを巧みに設計し、その特性を明らかにすることで、新構造高分子、物質表面機能化、有機-無機複合材料などの、次世代高分子材料に向けた反応性オリゴマーの開発を行っています。 |
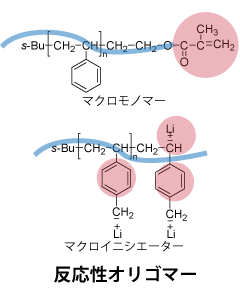 |