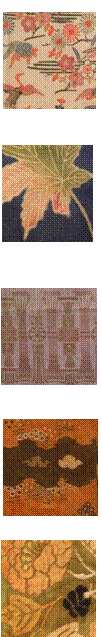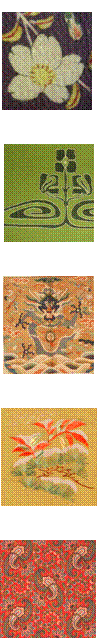裂地展のためのメモランダム 挨拶に代えて
京都工芸繊維大学美術工芸資料館 館長 竹内次男
|
|
標本台帳に数える染織関係の資料は他の分野の資料に較べて圧倒的に多い。それは色染科、機織科そして図案科という明治 35 (1902)年の京都高等工芸学校設立時の学科構成の故である。また、東京遷都以後廃都と呼ばれてもよい程に荒廃した京都の復興計画という政策実現の為の推進を承けて京都の地場産業並びに広くわが国の産業界及び学校設立の主体であった政府、特に、これを主導する立場にあった文部省の新規に設立させた国の直轄学校に託した意図、そしてそれに応えようとする学校関係者の意欲と尽力の大きさの程を反映していると想われるからである。この度は、染織資料関係の中から特に裂に焦点を絞り、その調査・研究結果の報告である。 裂地として収集され、後に裂地帖に仕立てられたものが多い。収集時より裂地帖の体裁をとっているのは、取り分け、江戸期から明治期に関連の機屋、染屋、企業が染め織りの見本帳として綴り纏めたもので、標本台帳を見ると大正15(1926)年6月に京都西陣のとある織屋の廃業に伴い、資料の散逸を防ぐ為一挙に収集の運びとなり、受け入れ現在につたえられているものが多い。 外国品或いは外国産と銘記された標本・資料−多くは稲畑勝太郎商店により購入のパリのクロード・フレール社の製品の裂である− は、受け入れ後本学に固有のフォーマットに仕立てて裂地帖とされている。標本台帳を辿ると明治35(1902)年から昭和10(1935)年頃までクロード・フレール社の裂見本を継続的に収集している事が判るが、これは或る意味で非常に息の長い収集活動と言わなければならない。何れにせよ教材や研究素材として集められたと推量される極く小さな裂地の具体的な本学に於ける使用目的に就ては未だ詳かではない。或る裂地に関しては想像を逞しくすることによってそれを推し量ることも出来ようが、大略全面的に不明である。 裂地に関する調査・研究の成果を問うべき今回の展覧会は、「本学染織資料調査研究会」を発足させてから、既に5年の長きに亘る地道な調査・研究活動から得た成果である。 |
|
|
開校以来京都染織業界をリードしてきた京都工芸繊維大学が多年にわたって蓄積してきた桃山時代から大正時代までの国内外未公開染織資料の集大成 展示資料:匹田縫(AN.106:国立歴史民俗博物館所蔵野村コレクション小袖屏風、斜格子菊吉祥文模様腰巻(資料番号H-35-16伝東福門院)の分裂)、色染標本古裂地見本帳( (オランダ製)(AN.71)東京国立博物館にコレクションあり)、秩父宮殿下御成年式服裂地帖(AN.2517)本学作成)、婦人服地絹布類裂(AN.608クロードフレール商会(パリ))、図案標本(織物地)捺染綿地(AN.824、リバティー・プリント、1903年購入)等 |
||
|
図版 左上から琉球紅型染裂(AN.546) ▽友禅染標本帖(AN. 38-1-23) ▽友禅染標本帖(AN. 38-1-23) ▽縫の打敷、撫子模様(AN 416) ▽萌葱地牡丹唐草文様唐織裂(C-a-3) 右上から▽友禅染標本帖(AN.38-1-14) ▽窓掛地 (AN.1037) ▽波涛龍文様綴錦の寄せ裂装飾幕(AN.374) ▽ヒワ縮緬に縫打敷(AN.415) ▽染色標本(AN.28-8-2-7) |
||